豚熱乗り越え地域の農業をけん引
2022.06
飼養技術の高さから岐阜県の共進会で毎年のように入賞する、ムトウ畜産の武藤政臣さん(43)。地域の農業をけん引する武藤さんに、養豚への思いや豚熱からの再建についてお聞きしました。

「自分は恵まれている」気づかされた大学時代
「幼い頃は家で豚を飼っているのが嫌で、実家が養豚農家であることを隠していた」と話す武藤さん。プロ野球入団テストを受けたいと願っていた野球少年時代は、家業を継ぐつもりは一切ありませんでした。
養豚への思いが変わったのは大学生時代。北海道にある酪農学園大学に進学すると、畜産に夢を抱き就農を目指す多くの学生と出会いました。
両親が休みなく働く、家畜のにおいが漂う家業を嫌っていましたが、「何一つ不自由のない暮らしをさせてもらい、車を買ってもらったこともある。自分は恵まれているんだと気づき、養豚農家であることを胸を張っていえるようになった」と振り返ります。
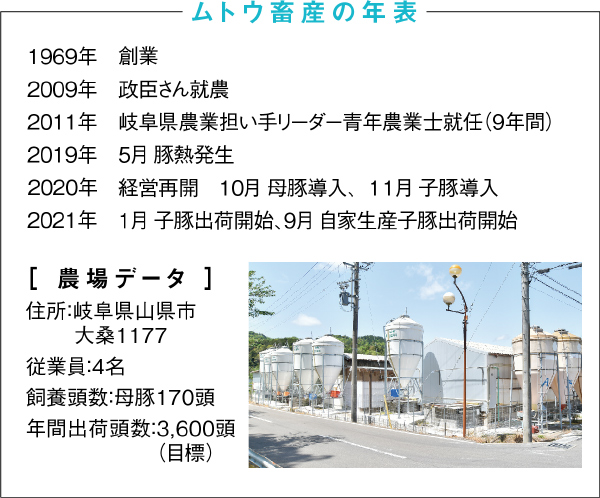



父から指示されるだけの毎日 飼養管理の本質知り“開眼”
家業に入ったのは、大学を出て食肉卸で8年ほど勤めたあと。母親が農作業で疲れてつらそうにしているのを見て「楽にしてあげたい」と思ったのがきっかけでした。しかし、就農したものの「分からないことばかり」。父親は「こんなことも分からんのか」と厳しく、同世代の養豚農家は既にベテランの域。「今さら誰にも何も聞けず、指示されて作業するだけの嫌な毎日でした」。
転機が訪れたのは32歳。JA全農の飼料畜産中央研究所での研修でした。座学と実習を通じて飼養管理の技術を学び、その知識を家業で実践しました。発情の見極め、人工授精、病気の早期発見と対処など、一連の作業の意味を理解して目的を持って実践すると、豚の受胎率が見違えるほど向上し、死亡率も低下して、出荷頭数が年間400~500頭ほど増加。「ようやく父親から認められるようになった」と手ごたえをつかみました。

豚熱発生し全頭処分 絶望の底から「責任感」で再建
飼養技術を向上させた武藤さんは、枝肉共進会で毎年のように入賞する常連となり、高品質な豚肉の生産者として一目置かれる存在となりました。38歳で親から経営を引き継ぎ、地元のブランド豚肉「美濃ヘルシーポーク」の出荷者として消費者との交流にも参画。2011年から岐阜県農業担い手リーダー青年農業士を9年間務めるなど、地域の農業者の中核的役割を担っていました。
そんな順風満帆な経営が一転、廃業の危機に直面したのは2019年。岐阜県内で豚熱が多発し、周辺の農場にも広がりました。武藤さんの農場でも発生し、飼養していた全頭の処分を余儀なくされました。
空になってしまった豚舎に茫然自失し、自己嫌悪や疑心暗鬼に陥り心身ともに憔悴した武藤さんですが、廃業を選ばず経営再建に奔走します。家族や従業員の暮らしを支え、再建することで周囲に対する責任を全うしたいとの思いでした。母豚の導入、防疫対策のための施設改修や新たな設備導入、資金調達など困難を極めましたが、行政、JAグループや取引先など関係者の支援を得ながら再建にこぎつけました。


1年半ぶり出荷スタート 育てた豚の美味しさに自信
豚熱発生から1年半以上が過ぎた2021年1月。豚の出荷が再開しました。武藤さんは「自身で一から養豚を始めることになり、考え方が変わった」と感じています。
「(感染は)仕方ないこと。頑張って」といってくれた仲間たち、一度は辞めてもらった後も戻ってくれた従業員たち、「あんたのところの肉はいいね」といってくれる消費者…、応援してくれる人たちの気持ちに応えたいと考えています。
再建はまだ始まったばかり。「出荷頭数を豚熱発生前以上に戻したい」「防疫強化で大幅に増えた労働負担を改善したい」「従業員の給料と休みを増やしたい」「自分たちの育てた豚をもっと地元で食べてもらいたい」――。目の前に難題は山のようにありますが、「数年ぶりに自分の育てた豚を食べたら、本当に美味しかった」と顔をほころばせました。
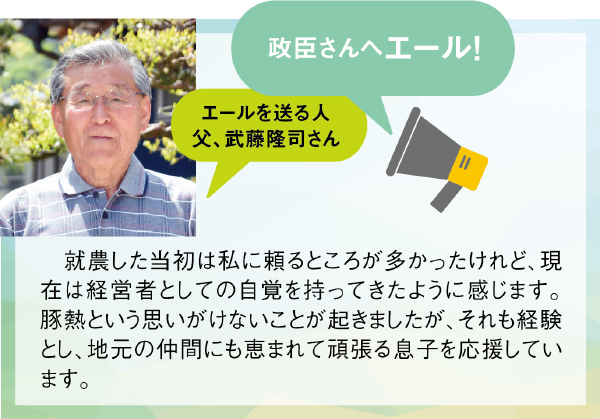
PDF: 509.96 KB



