第42回全農酪農経営体験発表会
~未来を創る 『酪農のなかま』~ 優良事例を共有
2025.04

JA全農は2024年11月20日、酪農経営の優良事例を発表する「第42回 全農酪農経営体験発表会」を東京・大手町で開いた。全国から6組の優れた酪農家と酪農家を支える組織が、日頃の取り組みを発表。厳しい酪農環境を業界一丸で乗り越えようと、参加者らは方策を探った。
同発表会はJA全農酪農部が主催。酪農家および酪農業界の発展に寄与することを目的に、全国で営農をしている酪農家の優良経営事例に焦点をあて毎年開催している。JA全農の由井琢也常務理事は、24年に発生した地震や台風などによる農業被害、昨年から続く生産コストの高止まりなど厳しい情勢が続き、全国の酪農家戸数が1万戸の大台を割りこむ状況となっていることに触れた。
厳しい現状を業界一丸で乗り越えていきたいという想いを込め、第42回発表会の副題は「未来を創る 『酪農のなかま』」。全国の酪農家とそれを支える組織が日々取り組んでいる優良事例を共有した。

常務理事 由井 琢也
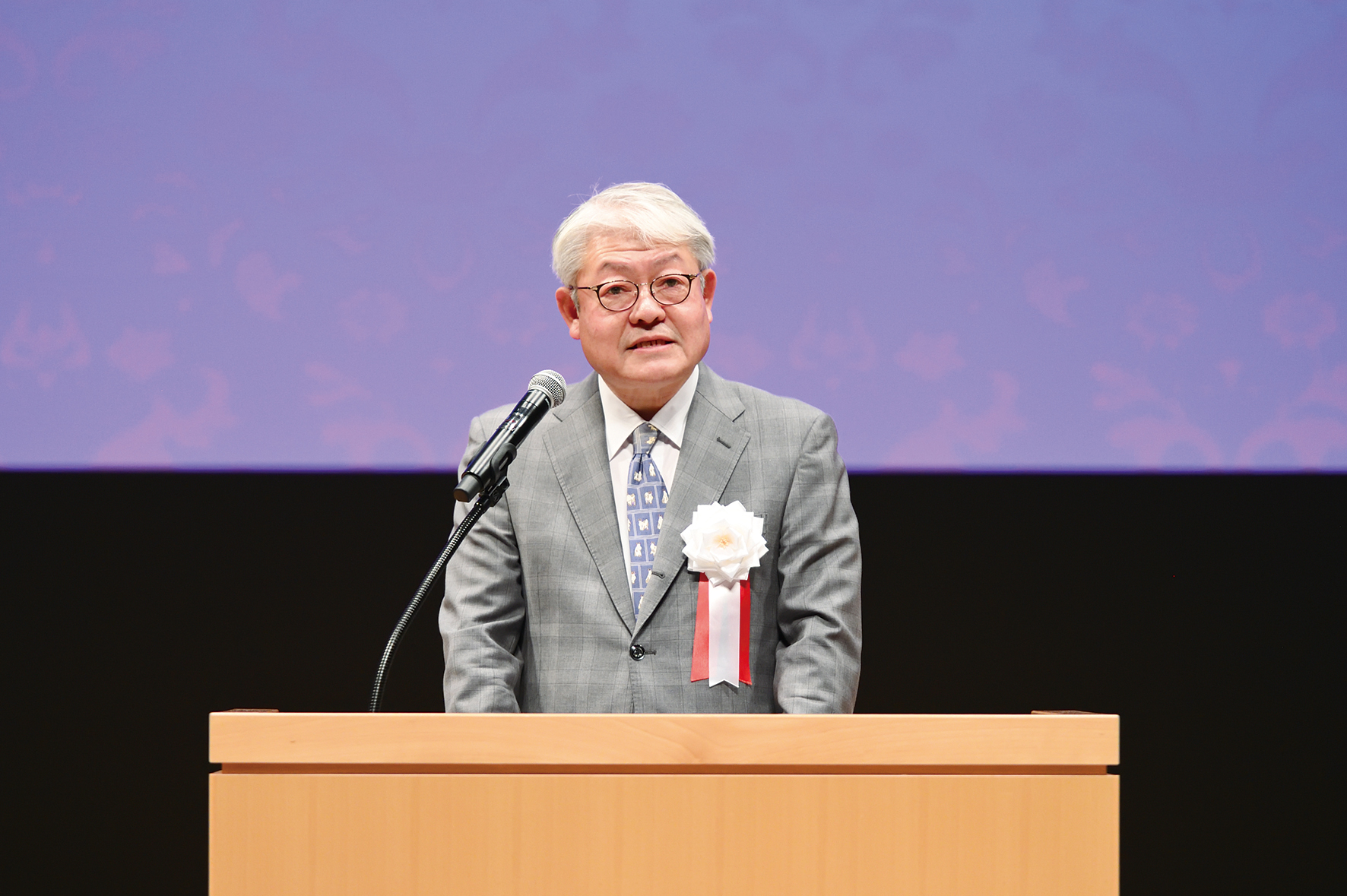
日本獣医生命科学大学 教授 小澤 壯行
大分県
牛飼いだからこそできる地域貢献
(有)はみんぐ・まむでは近隣農家や企業と連携し、地域循環型の自給粗飼料生産および未利用資源を活用したエコフィードの製造に取り組んでいる。また、地元小学校での酪農業の出前授業や久住高原の環境保全活動など、酪農業を通じた地域貢献に取り組んでいる。
講評
酪農経営の維持・発展において、地域での理解醸成は重要なポイント。自身の酪農経営にとどまらず、地域課題の解決や地域の教育・文化に貢献する姿勢に深く感銘を受けた。

志賀 拓馬さん
青森県
地域酪農の未来~新たな牧場経営を通じた地域活性化~

鳥谷部 大地さん
農家戸数の減少が続く青森県において、(株)北栄デーリィファームは地域の中核となる酪農経営体となることを目標に、県内初となる酪農協業法人として設立された。協業法人化によって、家族経営では困難だった規模拡大、自動搾乳機・ICT機器による省力化、および雇用体制整備による労働環境の改善などに取り組んでいる。昨今の飼料価格高騰対策としては、地域農家やトラクター組合と連携し、自給粗飼料生産基盤の確立など、地域の酪農業の安定・維持に貢献している。
講評
協業法人化によって、規模拡大や雇用条件改善による従業員の安定・定着など、農業経営体として成果をあげている。
千葉県
地域の特性を活かし効率化を追い求めた酪農経営
牧場経営と並行してアイスクリーム工房も運営している行木牧場は、飼料価格高騰を契機に労力面で休止していた自給粗飼料生産を再開。同じ農機で収穫できるように栽培作物を調節することで、機械への投資コストや作業時間を軽減している。また、ファームノートカラーによる発情発見やカメラを用いた分娩・牛群監視を行い、繁殖管理も省力化する取り組みをしている。
講評
さまざまな手法で農場運営の省力化を実行しながら、アイス工房のような6次化や自給飼料生産の規模拡大などさらなる経営改善に挑戦していることが素晴らしい。

行木 達哉さん
栃木県
サラリーマンからの転職~研究職で培ったチャレンジ精神~

大門 正英さん
大門正英さんは電子材料メーカーに研究職として12年間勤めた後に就農。就農直後から自牧場の営農データを分析し、経営課題を洗い出した。その後、JA全農くみあい飼料株式会社と連携しながら、夏場の乳量低下を防ぐための暑熱対策や、子牛育成管理を見直し、着実に経営改善を達成していった。
講評
酪農の専門教育を受けていないにもかかわらず、研究職経験を生かした独自の分析力で乳量や繁殖成績を改善し着実な成果を上げている。地域の酪農協や飼料会社から支援を受けつつも、自ら情報を取捨選択し、堅実に農場経営を改善していく姿勢を高く評価したい。
滋賀県
牛を大事に! 大切に!!
(株)メアリーファームは「牛にとって最良の環境をつくる。滋賀県で一番牛に優しい牧場」を目標に、新牛舎を設立。23年時点で経産牛230頭まで規模拡大した。年2回の全頭削蹄の実施、トンネル換気や冷水ミスト散布システムの導入など、乳牛の快適性を重視した営農方法で、搾乳量の増加・乳成分値の向上を実現した。
講評
社長や従業員のこだわりが新設した牛舎のあらゆる場所に見られ、まさに酪農家の夢のような牧場となっている。堆肥舎については、全国の施設を視察して学んだ優良事例を基に作られた素晴らしい設計で、他の地域の堆肥センターにも参考になるものである。

葭谷 健一さん
北海道
(株)Farm to-moを架け橋とした未来の友づくり

横内 整さん(左)
(株)Farm to-mo
武藤 元成さん(右)
JA北オホーツクでは、高齢化と後継者不足による酪農家戸数減少に歯止めをかけるため、次世代の酪農後継者を育成する研修牧場Farm to-moを設立した。同牧場では哺育から成牛まで一貫した飼育管理技術を学べる他、搾乳ロボットなどの活用法なども学ぶことができる。
講評
研修が非常に弾力的なものになっており、いろいろなタイプの酪農経営技術を学べるようになっている点が特徴的だ。研修後は、新規就農だけでなく、法人経営牧場や酪農ヘルパーとしての就職支援なども行っている。地域の酪農業を支える組織としての役割を体現していることを高く評価した。
第18回全農学生「酪農の夢」コンクール

第18回全農学生「酪農の夢」コンクール表彰式も同時開催された。将来の日本の「酪農」を担う畜産・酪農・農学等を学ぶ学生から、「酪農の夢」をテーマに作文を募集。本年度は応募作品120点から9点の作品と、学校賞として2校が入選した。
最優秀賞は、岡山県立高松農業高等学校畜産科学科2年の坂上凜さんの作品「アリスからの贈り物」。坂上さんは高校で世話をしていた乳牛アリスが病気によって早期出荷を迎えてしまった経験から、飼育者として命を預かる大切さ、目指す理想の酪農家像について発表した。
PDF: 933.01 KB



